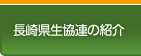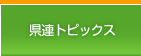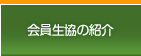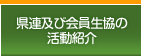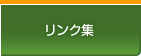県連トピックス
2025ピースアクションinナガサキの開催報告について
2025年8月7日(木)~8日(金)の2日間にわたり、長崎市民会館を中心とした3会場で、「被爆・戦後80年 平和とよりよい生活のために~ナガサキから戦争も核兵器もない平和な世界の実現を!!~」をテーマに2025ピースアクションinナガサキを開催しました。
今年は、次世代への継承をテーマに若者たちが、被爆80年をキーワードにディスカッションする企画「NEXT PEACE」および、「継承者(被爆3世)による二重被爆の証言」、そして、東京大学大学院渡邉英徳研究室の最新テクノロジーを駆使した「ミライの平和活動」、「デジタルアーカイブ体験会」、「平和のかけら」を開催しました。
また、虹のひろばでは、今回初めて広島の被爆者である八幡照子さんを招き、「被爆の証言」の講演をしていただきました。ロビーでは、鈴木賢二作の「平和を世界に」の版画絵巻を展示しました。
その他、これまで開催している「室内碑めぐり」、「被爆の証言」、「平和の紙芝居」そして、「平和のまち歩き」を実施し、 トータル9つの分科会と虹のひろばを開催し、県内外含め、40生協・延べ人数1,925人(オンライン視聴含む)の参加者がありました。
【第1日目 8月7日(木)】
 |
| 講師の城臺 美禰子さん |
〈1〉室内碑めぐり/城臺 美禰子さん
◆13:30~15:00
(司会)ララコープ/中島理事
会 場:長崎市民会館6階第7・8会議室
参加者:11生協・50人
城臺美弥子さんとお孫さんお二人で爆心地から城山小学校までの碑めぐりをプロジェクターで画像を投影しながら説明しました。はじめに、城臺さんよりご自身の戦争・被爆体験をもとに、平和とは、ご飯を食べられること、学校に行けること、家族団欒ができること、帰れる家があること、安心して眠ることができること等の話があり、戦後80年は平和な日常だったが、これからの80年、同じような平和が続くだろうか。今の世界と日本の情勢を見ると、とても心配と話されました。その後、日本が村にまで学校を作り国民の教育に徹底的に力を入れ、兵力を増し、戦争を行い、原爆が落とされるまでの歴史と、戦時中の生活(防空頭巾の事例)の話がありました。最後に、城臺さんより「戦争は二度と行ってはならない。それが私の願いです」と話を締めくくられました。
参加者からは、「浦上川に多くの被爆者が水をもとめて入水し、たくさんの方が亡くなった。その話を聞いて、戦争を行うことは、胸が痛くなる」との感想がありました。
〈2〉ミライの平和活動/東京大学大学院 渡邉教授
◆13:30~15:00
(司会)ララコープ/松本理事
会 場:長崎被災協地下1階講堂
参加者:11生協・45人
「ミライの平和活動」東大渡邊研究室」が作成した、ヒロシマ、ナガサキ原爆の画像や証言をまとめた3D地図をもとにヒロシマとナガサキの被害情報の違いを紹介し、マップ化することで過去の出来事と現在とのつながりが見えてくるとの説明がありました。そして、過去の白黒写真をカラー化することで、過去の出来事、遠くの出来事をより身近に感じることができ、さらに画像のカラー化により、その人、その風景が確かに実在していた実感が湧いてくるとの説明があり、その後、「交流証言者」として継承活動を行っている荒木千尋さんより、被爆者である「中村一俊さん」の被爆の証言を行い、その後グループ交流および、質疑応答をして終了しました。
会場の参加者からは、「渡邉教授の話や活動がとても良かったです。昔の写真をカラーにするだけで身近な感覚になりましたし 昔の地図と現在の地図を重ねることでより分かりやすくなりました」、「荒木さんの活動にも感動しました。これからを生きる私達や子供たちができること、自分の事として考えることの大切さがよく伝わりました」等の感想がありました。
 |
 |
|
| 講師の渡邉教授 | 熱心に聞き入る参加者 |
 |
| 会場の参加者 |
〈3〉デジタルアーカイブ体験会/東京大学大学院渡邉研究室
◆15:45~16:45
(司会)ララコープ/里中理事
会 場:長崎被災協地下1階講堂
参加者:13生協・57人
講師に東京大学大学院 渡邊研究室の村山 美那子さんを迎えの開催となりました。最初にストリートマップで考える被爆体験の継承についてお話しがありました。
村山さんは平和学習の形骸化に問題意識を持ち、原爆被害においては国際的な視点を大切にして世界中の人々が共有できるのが理想と言われました。
そして、ストリートマップでは地図と画像、動画を組み合わせているので、その場に行かなくても、目的地周辺の土地の様子や空気感を確認することができ、平面写真とは違ってより臨場感を味わえると説明がありました。
参加者は、スマートフォンからQRコードを読み取り、広島と韓国の被爆者が生まれた場所、通った小学校、生活していた場所、被爆した場所、ピースボートに乗って被爆の証言されている様子が地図上に描かれており、参加者は熱心にスマホを操作しながら、ストリートマップの情報を確認していました。
〈4〉子ども平和会議
◆13:00~15:30
(司会)ララコープ/新山理事
会 場:長崎市役所2階多目的スペース
参加者:3生協・11人
最初に講師のピースバトン代表の調さんより、被爆当時の状況説明と、実際に使用していた食器や中学生の制服を目で見て確認しました。また、東京大空襲での死者数(10万5400人)や沖縄陸上戦では、県民の約4割(20万人)が犠牲になったこと、そして広島(リトルボーイ)と長崎(ファットマン)に落とされた原爆について説明がありました。その後、2グループに分かれて、活水高校平和学習部の生徒4名がグループの進行役に入り、調さんの説明を聞いての感想、今後どうすれば戦争がなくなる世界になるかなどの意見交流をしました。
参加した子どもたちからは、「戦争は決してしてはいけない」、「未来を考えた活動をしないといけない」といった感想が寄せられました。子どもながらにも、平和について一生懸命に考え、意見を述べるのを見て、次世代への期待が持てる分科会となりました。
 |
 |
|
| 調さんの話を熱心に聞く子どもたち | グループに分かれ意見交流 |
 |
| 語り部の三田村さん |
〈5〉被爆の証言(平和の紙芝居)/三田村 静子さん
◆15:45~16:45
(司会)グリーンコープ/樋上理事
会 場:長崎市民会館6階第7・8会議室
参加者:14生協・81人
はじめに、原子爆弾の3つの恐ろしさ、特徴を参加者が想像しやすいように日常生活(建物や山の高さ・お風呂のお湯など)に例え、自身の体験も踏まえて説明しました。その後、平和の紙芝居「髪留めがくれた命」と「お母さんが焼いた運動場」を行いました。三田村さんから発せられる朗読に、参加者は真剣に耳を傾けていました。
質疑応答の時間では、子どもさんから大人まで質問・感想があり、開催後、多くの参加者が三田村さんのところに集まり声をかけ、写真を撮り、交流を行っていました。
参加者からは、「お母さんを焼いた運動場」の紙芝居はとても悲しく辛いお話で自分だったらと考えた時、同じように運動場での出来事が忘れられないと思いました。紙芝居を通して擬似体験ができ、日常のありがたみが分かります。との感想がありました。
 |
| 会場に参加した方々 |
〈6〉平和のかけら/東京大学大学院渡邉研究室
◆15:45~16:45
(司会)グリーンコープ/石原理事長
会 場:長崎市役所2階多目的スペース
参加者:4生協・14人
東京大学大学院 渡邉英徳研究室の研究院生と、長崎大学 核兵器廃絶研究センター(RECNA)から客員研究員の西山心さんが講師を務め、次世代向けの平和教育ツール「平和のかけら」を使用して、『被爆・戦後80年 平和とよりよい生活のために~ナガサキから「戦争も核兵器もない平和な世界」の実現を!!~』をテーマに講演を行いました。ワークショップ形式で進行していき、3枚の写真を見てそこに写る人物の気持ちを考えたり、平和と戦争の違いを考えてたり、作業シートに記入していことで講演を聞くだけではなく、しっかり参加しながら平和について考え、より深く学ぶ機会になりました。
参加された方からは、「今まで参加した分科会とは少し違って新鮮な学びだった」、「なんでもない日常が実は非常に大切な事だと改めて考えさせられた」、「おなじ写真をみても、人それぞれ色々な見方があることがわかった」等々の意見が出されました。
 |
| 平和のまち歩きをする参加者 |
〈7〉平和のまち歩き/平和公園コース、浦上天主堂コース
ガイド役は長崎のピースボランティア(高校生・大学生)10人・被災協平和ガイド1人 平和ガイド石畳の会6人
◆17:30~18:40
集合場所:爆心地公園
参加者:平和公園コース(12生協・52人)、浦上天主堂コース(16生協・74人)合計:126人
※当初は、100人を予定していましたが、大幅に上回る参加者の応募がありました。
平和公園内をめぐるコースと浦上天主堂までを巡るコースの2つに分かれて、長崎平和推進協会のピースボランティアの学生10人と平和案内人の7人がガイドをつとめ爆心地周辺や浦上天主堂の被爆遺構を巡りました。 今年も看護師さん2名に救護係をお願いしました。
今年は事前に実施要領を作成し、グループごとの案内版を掲げて出欠確認を行いましたので混乱もなく円滑に運営できました。
参加者は、興味深く平和ガイドの説明に耳を傾け、熱心にメモをとる姿がありました。
心配された天候でしたが、当日はほとんど降雨もなく、曇り空で比較的過ごしやすい天候でしたので無事に碑めぐりを実施することができました。
参加者からは、「爆心地公園には原爆当時の地層が残っており、当時の食器などが残されていました。当時、ここで生活していた多くの人々が犠牲になられたのだと気付かされました」、「爆心地から上空を見上げて、ここにあの原子爆弾が落とされたのかと思うと複雑な気持ちになります」等の声がありました。
【第2日目 8月8日(金)】
〈8〉被爆の証言/八木道子さん
 |
| 語り部の八木さん |
◆10:00~11:30
(司会)グリーンコープ/樋上理事
会 場:長崎市民会館2階視聴覚室
参加者:16生協・72人
講師の八木さんから被爆当日の市民の様子、原爆の恐ろしさ①凄まじい爆風(秒速/400m)、②熱線の温度は爆心地で3000~4000度、③放射線による健康被害が説明されました。
また、平和は黙っていてもやって来ない、積極的に取り組むもの。子どもたちには私たち被爆者の思いを次世代に継いでもらいたい。平和のバトンを繋いでもらいたいと話されました。
そして、現在、使える核兵器は9,615発(全部で12,000発)。1度でも使ったら、やり返す、またやり返すとなり、 地球は滅びてしまうとおっしゃられました。
そして、「赤い背中の少年」の谷口稜曄さんの写真は被爆から7か月後、2~3年間はうつ伏せのままの状態で普通に寝ることすらできなかった。最後に、戦時中に八木さんが使われていた防空頭巾を会場の子どもさんに被ってもらい戦争中の生活について詳しく説明されました。
参加者からは、「体験された生の声、非常に分りやすく説得力があり心に響きました」、「原爆の実相を知ること、それを回りの人に伝えること、小さなことだけれど自分にできることをやっていこうと思います。まずは家族へ伝えます」との声が寄せられました。
〈9〉継承者による二重被爆の証言/原田 小鈴さん
◆10:00~11:30
(司会)ララコープ/中島理事
会 場:長崎市役所2階 多目的スペース
参加者:8生協・39人
ヒロシマ・ナガサキで被爆した二重被爆者(ヒロシマ、ナガサキ)の山口彊(つとむ)さんの意志を継ぎ、2011年より次世代に語り継ぐ活動を行っているお孫さんの原田小鈴さんより、山口彊さんの人生を書き残された画像や映像などを通してお話がありました。
また、エノラ・ゲイ、ボックスカー搭乗員の孫、アリ・ビーザー氏との交流について説明をされました。
参加者からは、「被爆の証言のお話しを聞いて戦争の理不尽さを感じた。お話し、とても良かった。涙ながらに聞かせていただいた。私は中高の時代広島に住んでいて原爆の話を何度も聞くことはあった。もう二度と戦争は起きない思ってきただけにウクライナの戦争はとてもショックだった。今も続いているウクライナとロシアの戦争も初めは簡単に終わると思っていたのに終わりが見えない。日本は絶対に戦争をしてはいけないと思っている。特に核の問題については日本が先頭に立たないといけないと思っている。長崎では若い人達が頑張っているのを見てとても嬉しかった」との声がありました。
 |
 |
|
| 被爆3世の原田さん | 会場の様子 |
〈10〉NEXT PEACE-若者によるデイスカッション企画-
/ MICHISHIRUBE大澤新之介さん他、高校生平和大使、生協職員 合計:5人
◆10:00~11:30
(司会)ララコープ/玉城副会長
会 場:長崎市民会館 6階 第7、8会議室
参加者:10生協・67人
次世代に継承することを目的に、若者によるパネルディスカッションを行いました。ファシリテター役に平和をビジネスとする「MICHISHIRUBE」の代表理事である大澤さんを迎え、まずは、MICHISHIRUBEを立ち上げた経緯や平和×ビジネスの意味、そしてこの間の活動について報告されました。その後、ディスカッションに参加する4名の自己紹介を行った後、本題であるディスカッションに入りました。テーマは、①未来に向けて自分たちが出来ること、②ノーベル平和賞を受賞しての変化、③被爆80年の今、若い世代が担う記憶の架け橋とは、の3点について意見交換を行いました。
登壇者からは、「ノーベル平和賞を受賞することにより、外国人への平和の関心度が高まっている」、「核兵器廃絶運動に署名する人が増えた」、「戦争や原爆の怖さをどう継承して行くかが大切。常に継続した活動を行う必要がある」、「大きな括りではなく、身近な生活にもあり得る差別、偏見、いじめなどに眼を向けることも平和につながるのでは」などの意見が出され、有意義な分科会となりました。会場の参加者も若い方たちが目立ち、質問や意見が出されました。
 |
 |
|
| 大澤さん(左端)他登壇者4人 | 自分たちの活動について述べる県外の参加大学生 |
2025 ピースアクションinナガサキ 虹のひろば
 |
| 司会の古田 沙織 さん |
◆13:00~15:30
(司会)NBC長崎放送/古田 沙織さん
会 場:会場:長崎市民会館大ホール
参加者:31生協・756人 オンライン参加者56人を含む
ライブ配信(8/7~8/16)843視聴
今年は、「戦争も核兵器ない平和な世界を~被爆79年ナガサキの心を未来へ~」をテーマに開催しました。そして、昨年同様、県内外の参加者を会場に招いての開催となりました。最初に被爆者のご冥福を祈り、1分間の黙祷を行いました。
①日本生活協同組合連合会/代表理事会長 新井 ちとせ 主催者挨拶
 |
| 主催者挨拶 新井会長 |
8月7日(木)に原爆被爆者特別養護ホームを慰問しました。生協の役目として第一に「くらしと健康を守る」を目的としており、この慰問することにも意義がある。そして、本日開催する、2025ピースアクションinナガサキもこの一つだと言える。
ただ、昨今の世界情勢は、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとガザ地区の紛争等、不安定な状況にあり、核のタブーについても脅かされている。
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は、昨年の12月、ノルウェーのオスロにおいて2024年のノーベル平和賞を受賞した。これは、これまで核兵器のない世界を実現するため長年活動を行った結果である。そして、この席で田中熙巳代表委員が訴えた、武力ではなく対話で平和な世界を実現することは、地道に活動し続けることで実現出来ると確信していると述べました。
私たちは、「微力だけど無力ではない」この言葉を大切に、行政・他団体と一体になって平和な世界をともに作って行きましょう、とご挨拶されました。
②長崎市原爆被爆対策部長 阿波村 功一様 来賓挨拶
 |
| 阿波村部長 |
最初に生協の平和活動にふれ、「平和とよりよき生活のために」をスローガンにかかげ、本日開催の「虹のひろば」の開催や日頃からの継続的な活動について長崎県民の一人として非常に大事な活動であり、敬意を表したいと述べられました。その後、世界に目を向けると長期化するウクライナ危機や緊迫化する中東情勢などにより、核兵器が再び使用される脅威が高まっていることにふれ、こういった時こそ、このような流れに歯止めをかけるため、次代を担う私たちが被爆の実相を訴えること、活動の継承が必要だと述べられました。
そして、この「2025虹のひろば」は、若者による平和の活動報告もあり、次世代につなげる意味でも大切な企画だと認識している話され、最後に、この虹のひろばの成功と平和の一歩につながることを祈念しますとご挨拶されました。
③松井一實広島市長 来賓挨拶(ビデオメッセージ)
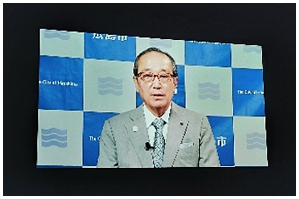 |
| 松井広島市長(ビデオメッセージ) |
2025ピースアクションinナガサキ 虹のひろばの開催への感謝の言葉のあと、核兵器の非人道性が再確認されるなど核兵器廃絶に向けた国際世論が大きくなっている。一方、長期化するウクライナ危機と緊迫化する中東情勢などにより、核兵器使用のリスクが懸念されるなど核兵器をめぐる国際情勢は混迷の様相を呈していると述べられ、続いて、日本政府は、核兵器禁止条約に署名・批准していないことにふれ、被爆国である日本がリーダーシップを取り、進めていくべきであると述べられました。 広島・長崎を最後の被爆地にするため、今後も他人を想いやる気持ちを大切にして継続的に核廃絶に向けた活動が重要であり、次代を担う皆様とともに核兵器廃絶の実現に向けて歩みを進めていくことをお誓いしたいとご挨拶されました。
④オープニング 雲仙市立小浜中学校吹奏学部
司会者より、雲仙市立小浜中学校吹奏楽部の「全国大会金賞受賞」や「笑顔がモットー」であることの紹介があったあと、演奏に入りました。
本日は、部員数20名が登壇して、演奏曲全3曲(ディズニーセレブレーション2曲、ヤングマン)を演奏しました、前半のディズニーセレブレーションは演奏しながら、行進とダンスも交えた元気と活気あふれる2曲でした。会場の参加者も拍手しながら盛り上がりました。後半のヤングマンはみなさんなじみの曲とあって、YMCAの振り付けを参加者と一体になって盛り上がるオープニングスタートとなりました。
参加者からは、「小浜中学校吹奏楽部はさすが全国に行くほどの実力で、実質10名の演奏なのにとても見応えがありました。若いって素晴らしい」、「元気で活気があり、オープニングに相応しい演奏だった」、「素晴らしいステージでした。初めて虹のひろばに参加したけど感動しました!」等の感想が寄せられました。
 |
 |
|
| 雲仙市立小浜中学校の吹奏楽部のオープニング | ||
⑤講演/俳優 斉藤 とも子さん
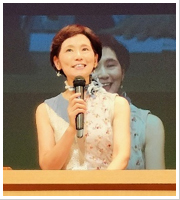 |
| 講演する斉藤 とも子さん |
はじめに、被爆者との親交のきっかけは、1999年、井上ひさし作の「父と暮らせば」のお芝居に出演した際、被爆者を演じたことにより、広島の被爆者との親交が深まりったのがきっかけとの説明がありました。その後、現状の世界に目を向けると各地で戦争が起きており、胸を痛めている。今は戦争をやっている場合ではない、今こそ命を大切に世界がひとつになり平和な世界を作らなければいけないと述べられました。そして、被爆・戦後80年を迎え、被爆者の方々は、辛い日々を一生懸命に生きてきた、どんなに苦しかったあっても懸命に生きてきた。これを無にしないよう、決して戦争はしてはいけない、2度と同じような過ちのないよう努めることが、次の世代の役割ではないかと思うと話されました。
そしてもう1点忘れてはいけないことが、2011年3月11日に発生した大地震に伴う、福島原子力発電事故の問題である。発生した当時、真っ先に被爆者たちは福島原発のことを心配していた。「差別を受けてはいないか」、「放射能は移るから近寄るな」とか・・・言われていないかと。今後も風化させることなく支援の活動を継続して行くことが必要である。
また核兵器保有国は、核兵器を持っていれば、つい使いたくなることもあり得る、そのためにも核兵器の廃絶を行う必要がある。そして何より命を大切にしてほしいと願う。と述べました。
そして、ひとり一人が真剣に戦争のない世界、核兵器のない世界を自分のこととして捉え、「みんなで力を結集して戦争のない世界を作ろうではないですか」と力強く締め括られました。
参加者からは、「斎藤とも子さんは子供時代に学園ドラマで活躍した憧れのお姉さんという印象でした。その後平和活動に尽力されていると聞き、今回講演があったので申し込みました。変わらず美しく、素晴らしい講演内容に感動しました。私も引き続き自分なりの平和アクションを続けていきます。有難うございました」、「斉藤とも子さんは女優さんということもあるのでしょうが、自分で感じたことを話してくださる熱量と迫力ある講演でした。心に響きました」等の感想が寄せられました。
⑥高校生平和大使活動報告・アピール文発表/子ども平和会議
 |
| 第27代高校生平和大使のみなさん |
第27代平和大使14名が登壇し、これまでの活動報告を行いました。1998年に長崎からスタートした高校生平和大使は、スローガンである、「微力だけど、無力ではない」を掲げ、その言葉通り、核廃絶の地道な署名活動(270万筆を越えた)やV・ファーレン長崎と連携したイベントに参加しての講演会、そして定期的な学習会と小学生を対象にした平和学習など多岐にわたり活動を続けていると述べました。
日本政府は、未だに核兵器禁止条約に署名していない、核の傘ではなく、過去の過ちに学び、早急に署名してほしいと思う。そのためにも、次世代である私たちがしっかりと継承し、活動し続けることが大切だと思っている。そして、平和の未来を作っていきたいと結びました。
発表後、「この声をこの心を」をアカペラで唄い、最後に、次の世代へ平和の大切さを継承して行きたい、若者の力を発揮したいと力強く決意表明されました。
参加者からは、「まだ10代だが、高校生平和大使の発表に刺激を受けた。自分たちも平和な生活を作っていけるように少しでも世の中の出来事に目を向けていきたい」、「平和は、何もしないと続いていかない。小さな行動でも大事だと思いました」、「微力だけど、無力ではない。本当にそのとおりで若い方たちの活動に頼もしく思う」、「将来に希望を持てる報告でした」等の感想が寄せられました。
アピール文発表/子ども平和会議
 |
| 議長2名が発表ん |
メンバーを代表して議長2名が、それぞれに平和のアピール文を発表しました。
被爆・戦後80年目の節目を迎え、講師の調さんの話を聞き、たくさんの気づきと学びがあった。
子どもたちとのグループ交流では、「黒い雨のことは知らなかった」、「埼玉での空襲のことは知らなかった。長崎だけではなく、もっと他県の被害についても目を向けないといけない」、「性別や年齢に限らず、いろんな人との交流が、気づきや学びに繋がっている。これからもいろんな交流を大切にしたい」等の意見があった。最後に、お互いが理解し合い、話し合うことが大切であり、次の一歩につながると信じていますと訴えて発表を終了しました。
参加者からは、「高校生が考えている平和と小学生が考えている平和が違って、こんな風に考えてるんだと学べたいい機会でした」、「戦争がとても怖いと思った。今戦争をしてない日本がずっと続いて欲しい」、「小中学生目線の意見を聞くことができてとても勉強になりました」と言った感想が寄せられました。
⑦長崎原爆被災者協議会/田中 重光会長
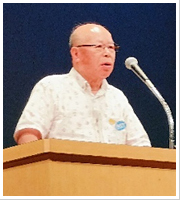 |
| 長崎被災協 田中重光会長 |
最初に、自身の被爆体験にふれ、爆心地から6km地点(時津町)で被爆し、時津町だけで380人余りの方がなくなられたこと。そして、家族が次々に亡くなり、その後も、地獄のような日々を過ごしたことについて被爆体験を話され、自分同様被爆者は、みんな辛く苦しい思いをして暮らしたこと、そして次々と亡くなっていったことについて切実に語られました。
しかし、世界に目を向けると、核兵器の脅威が増すばかりであり、非常に危機感を抱いている。「核のタブー」も危機的な状況にある。
また、日本政府は核兵器禁止条約に署名してなく、NPT再検討会議へもオブザーバーの参加さえしていない。これは、許しがたいことだし、今後も粘り強く訴え続けていく。最後に、「みんなで力を合わせて、核兵器廃絶への取り組みを進めていきましょう」と力強く、締め括られました。
参加者からは、「決して戦争は起こしてはいけないと改めて強く感じた」、「被爆者の苦労は計り知れないと思った。平和な未来を子どもたちに残すことが大切」等の感想がありました。
⑧広島から被爆の証言/八幡 照子さん
 |
| 講演する被爆者の八幡さん |
今回、ヒロシマとナガサキとの活動交流を図る意味含めて、ヒロシマの被爆者である「八幡照子さん」を招いて「被爆の証言」(講演)をしていただきました。
最初に、自身が8歳のときに被爆された体験について話されました。爆心地から2.5km離れた己斐(こい)本町(ほんまち)の自宅で被爆したこと、そして、家族8人がその場にいて、被爆した瞬間、5.6m程、吹き飛ばされ大けがを負ったことについて話されました。そして、周りには、腕の皮膚が、への字に曲げた手の指先にボロ布のように垂れ下がっている人、ただれた体を引きずって何十人、何百人の人が押し寄せてきて、もう地獄のような状況であったこと、そして市街地は一晩中燃え続けていたと話されました。
そして、8月9日には、火葬場と化した校庭を見て、何ともいえない、虚しさ、恐怖、悲しさを今でも忘れることが出来ないと実体験を語られました。
参加者からは、「八幡さんは絵画を交えてお話ししてくださって、よく分かりました。貴重な体験談を聞くことができ、改めて命の大切さと日常の平和の尊さを実感するkとが出来ました」、「被爆80年を迎えて、被爆に会われた方達の凄まじい体験談を聞けて、二度と原子爆弾を使うことのないよう、一人一人が心がけていかないといけないと思いました」等の感想がありました。
⑨フィナーレ 長崎南山小学校コーラス部
 |
| 長崎南山小学校コーラス部と卒業生のみなさん |
司会者から長崎南山小学校のこれまでの活動について紹介があり、その後、総勢40人の子ども達と卒業生15人が登壇しました。
曲目は、①Someshing beautiful for God ~あたたに捧げたい~②パプリカ、③祈り、の3曲を合唱しました。手話も交え、素晴らしいい歌声を披露しました。3曲目の「祈り」では、10年前に曲を作った際、作詞として関わった卒業生15名も合唱に加わり、更に花を添えました。
参加者からは、「コーラスがとても美しい声で子供達が平和を願う。感動しました。ありがとうございます♪♪」、「子どもたちの合唱、それを通じて平和への気持ちが伝わり、とても穏やかな気持ちになりました。受賞した実力通り、当日は素晴らしい歌声でした」等の感想が寄せられました。まさしくフィナーレに相応しい歌声だったと言えます。
⑩その他の企画/「虹のひろば」と同時開催
 |
| ユニセフすごろく |
●ユニセフすごろく&会場ライブ配信/佐賀ユニセフ協会対応
今回も託児とユニセフを知ってもらうきっかけにすることを目的に、「ユニセフすごろく」を開催しました。当日は、佐賀ユニセフ協会から2名と組合員要員2名、そしてライブ配信要員1名で対応しました。
親子4組(大人4名、子ども7名)が参加して、ユニセフすごろくを楽しみました。
●鈴木賢二作品「平和を世界に」の展示
被爆・戦後80年の特別企画として開催しました。栃木県出身の版画家、鈴木賢二(1906~87年)が描いた版画絵巻「平和を世界に」を市民会館ロビーに展示しました。平和な庶民の生活から大戦のはじまり、徴兵や疎開、ヒロシマ・ナガサキの悲劇、戦後の第五福竜丸の悲劇が描かれている。長崎の被爆者運動の礎を築いた渡辺千恵子さんの生涯を描かれていました。
当日、来場された方は、熱心に見入る方もいらっしゃり、平和のツールとして活用できました。
 |
※写真はイメージです
 |
| ロビー原爆パネル展示 |
●原爆パネル展/ロビーに展示
虹のひろば開始前と休憩時間や来場時、終了後含め、熱心に見て回る方たちがいらっしゃいました。戦争の怖さ、原爆の悲惨さ、平和の大切さを知るきっかけになりました。
また、文化ホールロビーにおいて、「碑めぐりガイドブック」等の販売、日本生協連ブース、生協総研ブースを配置して平和の大切さを訴えました。